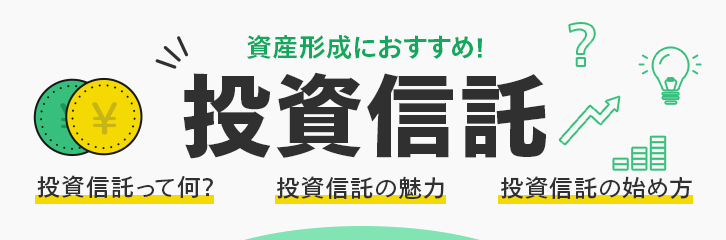1. 投資信託とは?仕組みをわかりやすく解説
投資信託(Investment Trust) とは、多くの投資家から集めたお金をひとつの大きな資金としてまとめ、運用の専門家(ファンドマネージャー)が国内外の株式や債券などに分散投資して運用する商品です。
運用によって得られた利益や損益は、投資額に応じてそれぞれの投資家に分配されます。
投資信託の仕組みと参加者
主な登場人物は以下の4人です。
|
登場人物 |
役割 |
具体例 |
|
投資家 |
資金を提供し、運用成果を受ける |
あなた |
|
委託者(運用会社) |
投資信託を設定し、運用方針を決定 |
野村アセットマネジメント、三井住友DSアセットマネジメントなど |
|
受託者(信託銀行) |
投資家から集めた資金を保管・管理 |
三菱UFJ信託銀行、みずほ信託銀行など |
|
販売会社 |
投資信託を販売する |
SBI証券、楽天証券、マネックス証券、銀行など |
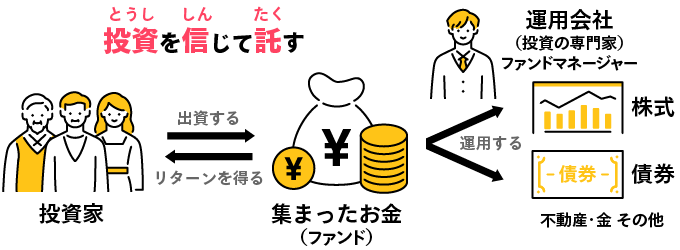
流れはシンプルです。
-
投資家が販売会社を通じて投資信託を購入する。
-
集められた資金は信託銀行で厳重に管理される。
-
運用会社のファンドマネージャーがその資金で投資を行う。
-
運用で得られた利益が投資家に分配される、または元本が値上がりする。
2. なぜ人気?投資信託の3つのメリット
1. 少額から始められる(分散投資の実現)
例えば、Amazonやトヨタ自動車の株を1株だけ買うには数万円必要です。しかし、投資信託なら1万円以下、場合によっては100円からでも、その投資信託が組み入れている何十、何百という企業に同時に投資することができます。これが分散投資です。
2. 専門家に任せられる
為替や企業分析は非常に時間と知識が必要です。投資信託では、その道のプロであるファンドマネージャーが情勢を分析し、投資家に代わって運用してくれます。自分で全ての銘柄をチェックする必要はありません。
3. 手間がかからない
特に、積立投資(つみたて投資) を利用すれば、毎月決まった日に決まった金額が自動的に購入されます。一度設定すれば、あとは放置しておけるので、忙しい方にも最適です。
3. 知っておくべきリスクと3つのデメリット
投資信託は元本保証された商品ではありません。 必ず理解すべきリスクがあります。
-
価格変動リスク:組み入れている株式や債券の価格は変動します。市場環境によっては元本を割り込む(損失が発生する) 可能性があります。
-
為替変動リスク:外貨建て資産に投資する場合、為替レートの変動によって損失が発生する可能性があります。
-
信用リスク:債券を発行している国や企業が破綻すると、元本や利息が返ってこない可能性があります。
デメリットとして、
-
コストがかかる:運用してもらう対価として信託報酬がかかります。
-
自分で銘柄を選べない:あくまでファンドマネージャーに任せることになります。
-
換金に時間がかかる場合がある:原則として売却指示から実際にお金が振り込まれるまでに数日~1週間程度かかります。
4. 初心者向け!投資信託の種類と選び方のコツ
投資信託は、投資先によって大きく分けられます。
|
分類 |
投資先 |
特徴 |
リスク目安 |
|
国内株式ファンド |
日本株 |
日本経済の影響を強く受ける |
高め |
|
外国株式ファンド |
海外株 |
為替リスクあり、成長可能性大 |
高め |
|
国内債券ファンド |
日本国債等 |
比較的安定、低金利 |
低め~中程度 |
|
外国債券ファンド |
海外債券 |
為替リスクあり、利率が高い場合も |
中程度 |
|
バランスファンド |
株と債券の組み合わせ |
バランスよく分散 |
中程度 |
|
REIT(リート)ファンド |
不動産 |
賃料収入を分配金で受け取れる |
高め |
初心者の選び方のコツは3つ!
-
インデックス型を選ぶ:日経平均株価やS&P500などの指数に連動するように設計されたファンド。信託報酬が安く、初心者にはおすすめ。
-
信託報酬が安いものを選ぶ:コストは長期運用で大きな差になります。1%以下のものを探しましょう。
-
積立投資に対応しているものを選ぶ:毎月コツコツ積み立てることで、リスクを平準化できます。
5. 実際に始めるまでの5ステップ
-
証券口座を開く:ネット証券(SBI証券、楽天証券など)がおすすめ。スマホアプリで簡単に開設できます。
-
資金を入金する:銀行口座から証券口座にお金を振り込みます。
-
商品を選ぶ:証券会社のサイトで、先述の選び方のコツを元に商品を探します。「つみたてNISA」対応商品から選ぶのが最も簡単です。
-
購入(または積立)の指示を出す:一度に購入するか、毎月の積立設定を行います。
-
継続して保有する:購入後は、短期の値動きに一喜一憂せず、長期的な視点で保有します。
6. 絶対に理解すべきコスト(費用)の話
投資信託には以下のようなコストがかかります。長期運用ではこの「コストの差」が「利益の差」になります。
-
信託報酬:運用してもらう対価。保有している間、毎日、基準価額から差し引かれる最も重要なコスト。年率0.1%~2%程度。
-
購入時手数料:購入時に支払う手数料。多くのネット証券では無料の商品が大半です。
-
信託財産留保額:換金する時にかかる場合のある費用。多くの商品ではかかりません。
「信託報酬」の影響を具体的に見てみましょう。
元本100万円、年間利回り3%で20年間運用した場合の差は?
|
信託報酬 |
20年後の評価額 |
コスト総額 |
|
0.2% |
約175万円 |
約5万円 |
|
1.0% |
約146万円 |
約34万円 |
信託報酬が0.8%違うだけで、約30万円もの差が生じます。
7. 成功のカギは「積立投資」にあり
積立投資は、毎月決まった金額を同じ投資信託にコツコツ買い続ける方法です。
-
平均購入単価を下げられる:価格が安い時は多く、高い時は少なく買うことになるため、購入単価が平準化されます。
-
習慣化できる:給与天引きのように自動で行うため、貯蓄が習慣化します。
-
感情による誤った判断を防ぐ:市場が下落しても自動で買い続けるため、「安い時に買う」 という投資の基本を自然と実践できます。
つみたてNISAを利用すれば、年間40万円までの投資から得られる利益が最長20年間非課税になります。初心者はまずここから始めるのが鉄則です。
8. 失敗案例と成功案例:Aさんの場合
【成功案例】Aさん(30歳・会社員)のケース
-
戦略:初心者なので、信託報酬が安いインデックスファンド(全世界株式インデックス)を選択。つみたてNISA口座で毎月3万3千円の積立投資を開始。
-
行動:コロナショックなどの暴風雨時も、感情に流されずに積立を継続。ニュースは気になるが、保有資産の細かい値動きは毎日チェックしない。
-
結果:10年間で元本396万円を積み立て。市場の成長もあり、評価額は約500万円に(利回り年約3.5%を想定)。コツコツ続けたことで、大きな資産を形成することに成功。
【失敗案例】Bさんのケース
-
行動:短期で儲け話に飛びつき、話題の特定国や特定セクターの高コストなファンドに集中投資。市場が少し下落しただけで慌てて売却して損失を確定。
-
結果:分散も積立もせず、感情的な売買を繰り返した結果、元本を減らしてしまった。
9. よくある質問Q&A
Q. いくらから始められますか?
A. 多くの投資信託は1万円以下、場合によっては100円から購入可能です。積立投資なら月々1,000円から始められる商品も多数あります。
Q. 損をしたら最大でいくらまで減る可能性がありますか?
A. 理論上、投資した元本がゼロになる可能性は極めて低いですが、半減する可能性はあります。例えばリーマンショック時には、全世界の株式は50%以上下落しました。あくまで余裕資金で行うことが大原則です。
Q. つみたてNISAと一般NISA、iDeCoは何が違いますか?
A.
-
つみたてNISA:積立投資専用。年間40万円、非課税期間20年。投資可能商品が限定されている(低コストのインデックスファンド等)。
-
一般NISA:都度購入がメイン。年間120万円、非課税期間5年。投資可能商品の幅が広い。
-
iDeCo:老後資金形成専用の私的年金。掛金が全額所得控除され、運用益も非課税。60歳まで引き出せないという制約あり。
Q. 分配金は多いほうがいいんですか?
A. 必ずしもそうではありません。分配金は投資信託の資産から支払われるため、分配金を出すとその分基準価額が下がります。羊毛を羊の体から刈り取るようなものです。再投資することで複利の効果が期待できるため、成長を期待する場合は「再投資コース」を選ぶのが一般的です。
Q. どの証券会社で口座を開けばいいですか?
A. 手数料が安く、取り扱い商品が豊富なネット証券がおすすめです(SBI証券、楽天証券、マネックス証券など)。自分が使いやすいアプリやサイトを比較してみてください。
【免責事項】
本記事は投資信託に関する情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定は、ご自身の判断でなさいますようお願いいたします。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。商品をご購入の際は、必ず最新の投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。